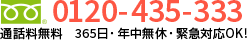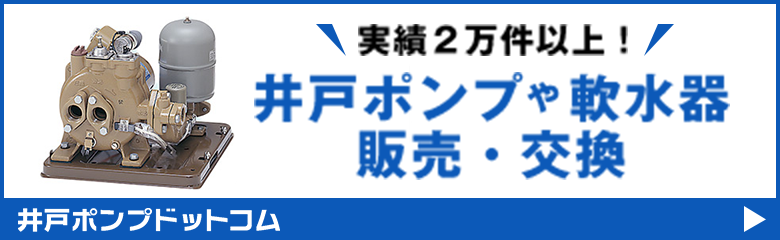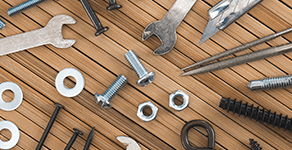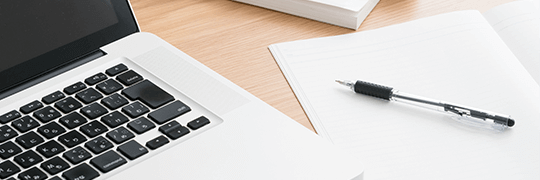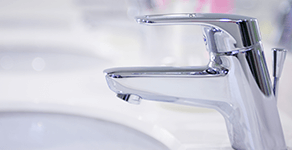水道の発達とともに、少しずつ姿を消していっていた井戸ですが、近年は災害時の頼もしい味方として改めて注目を集め、井戸の導入を検討している方が増えています。
井戸は、今も昔も私たちの暮らしを支え続けてくれています。
今回は、どんな場面で私たちの暮らしを支え続けてくれているのかをご紹介いたします。
暮らしを支え続けてきた井戸の長い歴史
古来から、文明が発展する際は水場を中心に人が集まり、町や村となっていきました。
「井」には集まるという意味や、留まるという意味があり、「戸」は場所という意味があるそうです。文字どおり、井戸は水が集まって留まる場所であり、また、人が集まったり留まったりする場所でもあったようです。
井戸の語源を見てみますと、川や湧き水などのような水を汲む場所のことも井戸と呼んでいたそうです。
さらに、湧き水を溜めておくために地表を掘っていたものも井戸と呼ばれていました。
井戸の起源はいつごろからというのは諸説ありますが、人間が定住生活を始めたころからだといわれています。
確かに、人間が一ヶ所に留まって生活するためには、水を安定して確保することが必要になります。
井戸の歴史は人間の定住生活とともに始まったともいえるのかもしれません。
井戸が私たちの生活へ与える知られざる功績
実際に、井戸が私達の暮らしのどんな部分を支えてくれているのか見てみましょう。
毎日の食卓に並ぶ食べものの中には、実は井戸水を使って生産されているものも多くあることをご存知でしょうか。
水道水で野菜やフルーツなどを栽培しているところもありますが、井戸水を使って栽培されているケースも多く、水を大量に安価で使用できる井戸は農業に適しているといえそうです。
もし、農家の型が水道水を使って農作物に散水していたなら、高額な水道料金が必要になります。その分野菜やフルーツの価格は割高となり、家計に占める食費の割合がグンと上がってしまうことでしょう。
井戸は私たちの毎日の食卓を支えてくれているだけでなく、家計も支えてくれているといえそうです。
身近な日用品や衣料品にも使われている井戸水

井戸水は工業用水としても多く使われています。
毎日当たり前のように使っているティッシュペーパー、トイレットペーパー、キッチンペーパーなども、大量の水がなければ作ることができません。
こうした日用品の生産にも、井戸水が利用されています。
衣類を染色する際にも大量の水が必要とされるため、井戸水が活躍しています。
井戸水を使うと衣類がゴワゴワになってしまうのではないかとお思いの方もいらっしゃるかも知れませんが、水質改善技術の進歩によって軟水に変えることが出来ますのでふわりと柔らかな仕上がりになります。
はるか昔から現代に至るまで、目に見える形ではなくとも井戸は私たちの暮らしを支え続けています。
今まで以上に、井戸をより身近な存在に感じられそうですね。