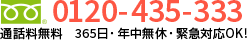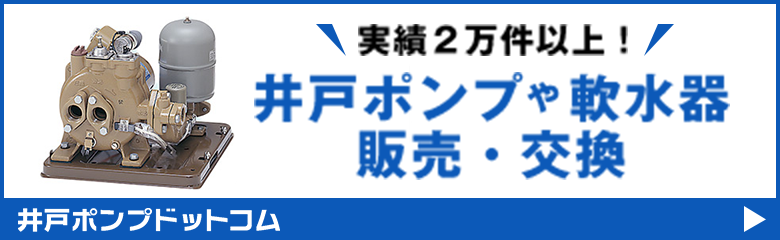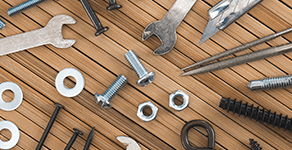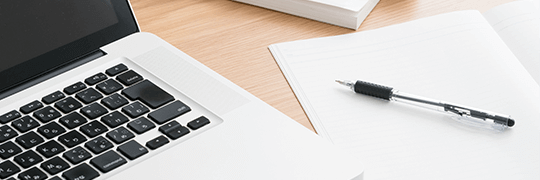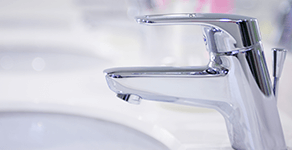暑い日が続くと、つい手が伸びるのが冷たいペットボトル飲料です。
シュワッと爽やかな炭酸飲料や、甘みのあるスポーツドリンクが喉を潤してくれる一方で、「ペットボトル症候群」と呼ばれる現代病のリスクが潜んでいることをご存知でしょうか?
便利な飲料が身近にある時代だからこそ、正しい水分補給の方法を知り、健康を守る意識が大切です。
今回は、ペットボトル症候群とは何か、その原因や対策、日常生活に取り入れたい水分補給のコツについて、わかりやすく解説していきます。
ペットボトル症候群とは?
「ペットボトル症候群」は、正式には「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれ、糖分を多く含む清涼飲料水や甘いコーヒーなどの飲み物を過剰に摂取することによって引き起こされる健康障害です。特に暑い季節や運動後などに、何本も飲んでしまうような習慣がある人は注意してください。
この症候群の主な原因は、糖分を大量に含んだ飲料を継続的に摂取することで、血糖値のバランスが崩れ、インスリンの働きが追いつかなくなることです。
通常、糖分を摂取すると血糖値が上がり、それに応じてインスリンが分泌され、血糖値を正常に戻す働きが起きます。しかし、甘い飲料を過剰に飲み続けると、インスリンの分泌や作用が間に合わず、高血糖の状態が続くことになります。
この状態が進行すると、身体はエネルギー不足を補おうとして脂肪を分解し始めます。その過程で「ケトン体」と呼ばれる物質が生成され、体内に蓄積されていきます。
これが「ケトーシス」という状態で、倦怠感やイライラ感といった症状を引き起こし、さらに進行すると「ケトアシドーシス」と呼ばれる過剰な酸性状態となって意識障害などを引き起こすこともあります。
特に注意したいのが、健康な若者でも発症するリスクがあるという点です。運動後にスポーツドリンクをがぶ飲みする人や、のどの渇きを癒やすためにジュースや炭酸飲料を頻繁に飲む人が無自覚にこの症候群に陥ることがあります。もちろんペットボトルだけでなく、糖分が入った飲料であれば、紙パックや缶でも同様です。
ペットボトル症候群を防ぐ! 水分補給のコツについて

私たちの体の約60%は水分で構成されています。そのため、日々の生活のなかで適切な水分補給を行うことは、体温調節や老廃物の排出、栄養素の運搬など、生命維持に欠かせない重要な役割を果たします。しかし、ただ「水分を取ればいい」という考えでは不十分で、摂取する内容やタイミングを誤ると、かえって健康を損なうリスクもあります。
水分補給は「水」または「お茶」を基本に
まず意識しておきたいのは、水分補給の基本は「水」または「無糖のお茶」であるということです。水には糖分やカフェイン、添加物などが含まれておらず、体への負担が最も少ない飲料です。ミネラルウォーターや浄水された水道水で十分に対応できます。
また、麦茶やそば茶、ルイボスティーなどノンカフェインのお茶も、日常の水分補給には適しています。特に夏場は冷やして飲めば口当たりも良く、熱中症対策にも効果的です。
運動時や発汗が多い時の水分選び
汗をかいたときには、ただの水だけではなく「ナトリウム(塩分)」や「カリウム」などの電解質を同時に補うことが大切です。特に長時間の運動や屋外活動時には、体から水分と一緒にミネラルが失われるため、経口補水液や、電解質を含むスポーツドリンクが有効です。
ただし、市販のスポーツドリンクには糖分が多く含まれていることがあるため、希釈して飲む、あるいは「低糖タイプ」を選ぶといった工夫が必要です。
また、手作りの塩レモン水(例:水500mlに塩ひとつまみとレモン汁少々)も、手軽に電解質と水分を同時に補える方法としておすすめです。
一度に大量に飲まない
水分補給は「一気に大量に」ではなく、「こまめに少しずつ」が基本です。1回で摂取できる水分量は限られており、一度に大量に飲んでも吸収しきれず、かえって胃腸に負担をかけてしまうこともあります。
理想的なのは、喉が渇く前に意識的に水分を摂る習慣をつけることです。特に高齢者や子どもは脱水に気づきにくいため、時間を決めて少量ずつ摂取するように心がけましょう。
体にやさしい飲み物で健康への第一歩を

何気なく選んでいる飲み物が、実は体に負担をかけているかもしれません。正しい水分補給は、健康維持の基本であり、毎日の習慣から見直すことができます。
ペットボトル症候群を防ぐためにも、「喉が渇いたから甘い飲み物を飲む」という選択を見直し、水やお茶など、体にやさしい飲み物を意識して取り入れてみましょう。健康を守る第一歩として、賢い飲み物選びを今日から始めてみませんか?