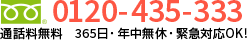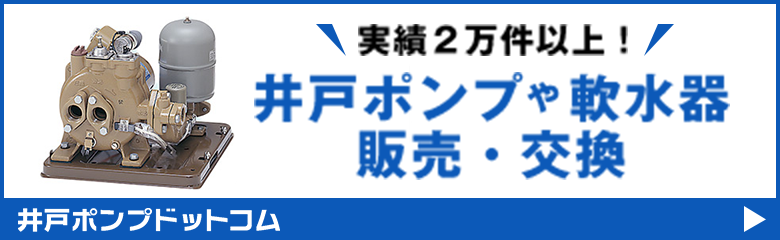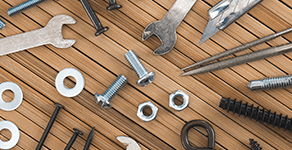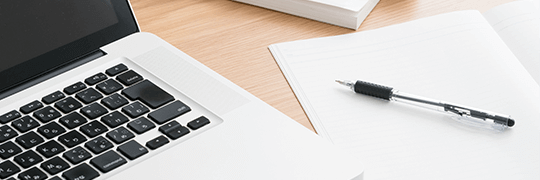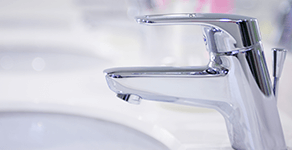近所の川や湖の水が濁っていたり、異臭がしたり、魚が減っていると感じたことはありませんか?
こうした現象の多くは、水域の「汚染」が原因です。水質が悪化すると、そこで暮らす生き物たちの命が脅かされ、人間の生活にも影響が出ます。
今回は、汚染された水域の原因や回復について解説します。
汚染された水域とは?
近年、温暖化の進行と同時に、集中豪雨や下水設備の老朽化が進み、これまで以上に水質悪化が起きやすい状況になっています。
中には汚染が進行していても見た目では気づきにくく、水が透明でも安全とは限らないケースもあります。
自治体が行う水質改善の予算も限られているため、市民一人ひとりの意識と協力が必要になっており、環境再生は「誰かの仕事」ではなく、私たち全員に関わる問題です。
一般市民にできることと専門家の役割
水質の回復と聞くと、自治体や専門機関、大企業が対応するイメージがあるかもしれませんが、実際には市民の行動も非常に重要です。
例えば、台所から油を流さないとか、洗剤の使用量を見直すだけでも、水質への影響を軽減できます。
一方で、汚染が進んだ水域では、科学的知見や技術をもつ専門家の手による対応が不可欠です。
汚染された水域の特徴と主な原因は?
水を汚す原因は一つではありませんが、最もよくあるのが「有機物」で、生活排水に含まれる残飯や石鹸などです。
「重金属」も危険で、工場から排出される鉛やカドミウムが代表的ですが、農薬や油類、プラスチック微粒子(マイクロプラスチック)など多岐にわたります。
生活排水は量が多くても、比較的有機物中心で自然分解されやすい傾向がありますが、工場排水は毒性の高い物質を含むことが多く、自然浄化では分解しにくい特徴があります。
両者が混在すると、水質回復がより困難になり、都市部では生活排水が主原因、工業地帯や農村では工場排水や農業排水が問題となるケースが多いです。
また、汚染の種類は河川・湖沼・海域ごとに違い、河川では都市部の排水による有機汚染、湖沼では富栄養化によるアオコの発生、海域では赤潮や油流出がよく見られるのが特徴です。
それぞれ地形や水の流れ方により汚染の進行パターンが異なるため、改善策も場所ごとに工夫が求められます。
水質の主な調査方法

水質を調査するには、「BOD(生物化学的酸素要求量)」や「COD(化学的酸素要求量)」といった基本的な数値を測定し、細菌や重金属の濃度を調べると、どのような汚染源があるかを把握できます。
BODは、微生物が有機物を分解する際に消費する酸素の量で、数値が高いほど汚れていることを示し、CODは、化学的に分解できる有機物の量を示し、こちらも高いほど水質が悪いと判断されるものです。
近年では、ドローンやIoTセンサーを使ったリアルタイム監視の取り組みも広がっています。
自然浄化と人工的な水質改善の違い
水には本来自然に汚れを分解する力がありますが、汚染がひどすぎるとこの浄化能力では追いつかず、完全に元の水質に戻るまでに数十年かかるケースがあります。
人工的には、汚れた底泥を取り除く「浚渫(しゅんせつ)」や、水中に酸素を送り込んで微生物の活動を促す「曝気(ばっき)」といった技術が使われますが、これらは短期間で効果が出る一方、コストや環境負荷も大きいため、導入には判断が必要になります。
そして、ヨシやミズゴケなどの水中の有害物質を吸収する力がある植物を使って自然に近い形で浄化する方法が「植物浄化法」です。
特に公園の池や小川のような、小規模な水域で導入しやすい特徴があります。
さらに最近注目されているのが「バイオレメディエーション」で、これは汚染物質を分解できる元々存在する微生物を増殖させたり、特殊な微生物を導入したりして水質を改善する方法です。
土壌や地下水の汚染にも応用されており、自然の力を使いつつ、科学技術の力を組み合わせた最新のアプローチです。
水域の回復には、元の環境に近い植物の選定と、段階的な植生回復が必要で、復元後もモニタリングと継続的なメンテナンスが必要になります。
汚染された水域を見過ごさない意識が大切

「少し濁っているだけだから」「昔からこんな色だったから」と見過ごしてしまうと、手遅れになります。
もし異変に気づいたら、まず地方自治体や関係機関に報告しましょう。
個人の力では難しくても、企業のCSR活動、自治体の補助金、市民のボランティアなど、地域全体で力を合わせて回復に取り組むことが大切です。